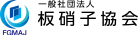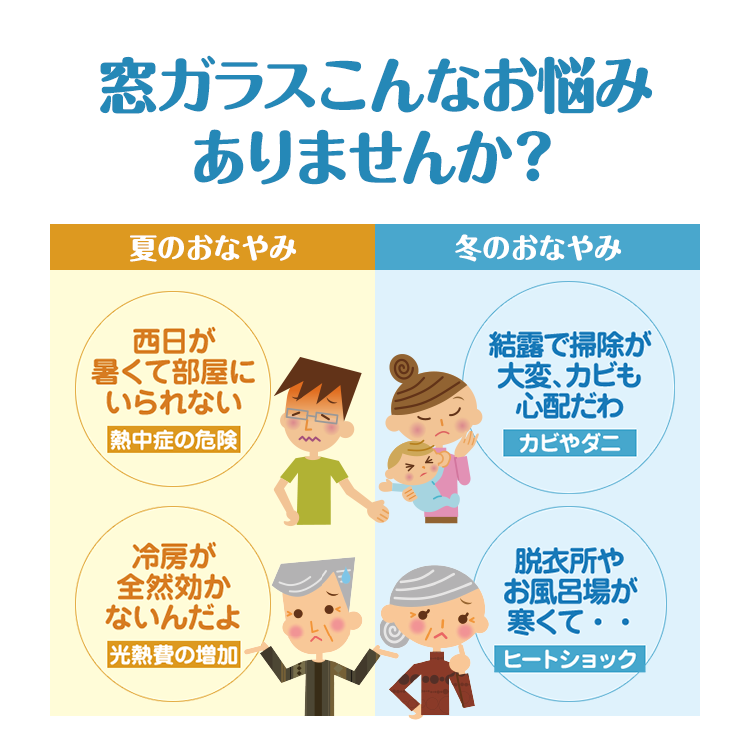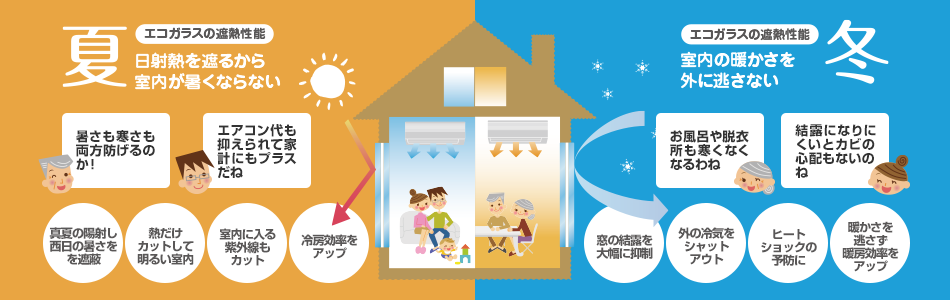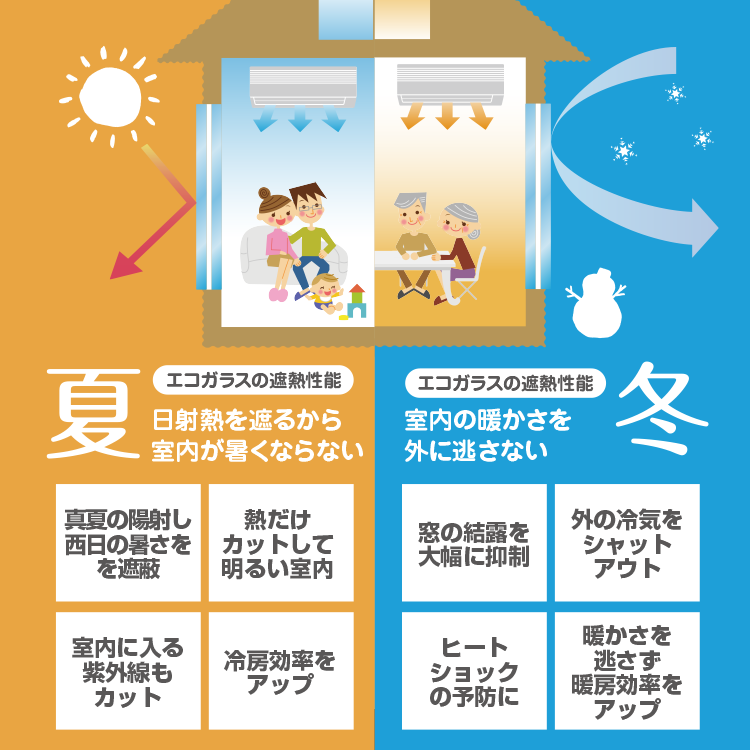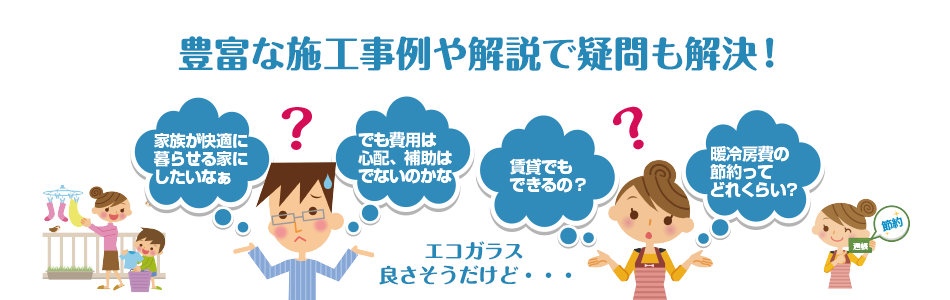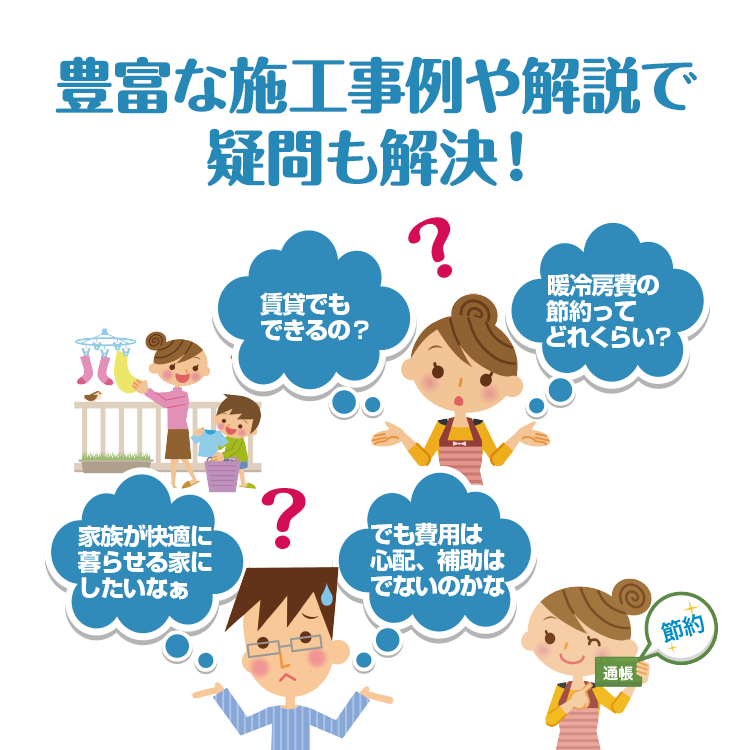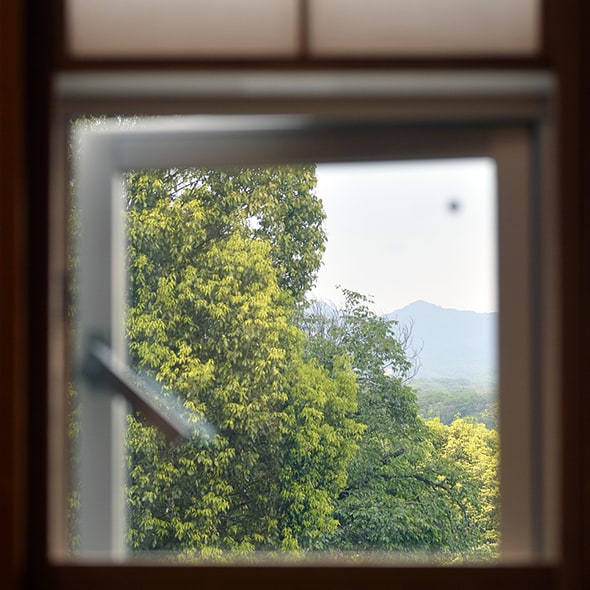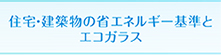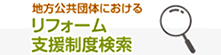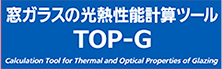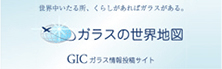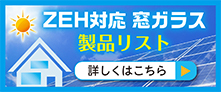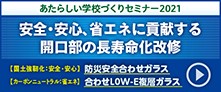動画やコラムでご紹介!
「板硝子協会ポータルサイト」

エコガラス
省エネ
シミュレーション
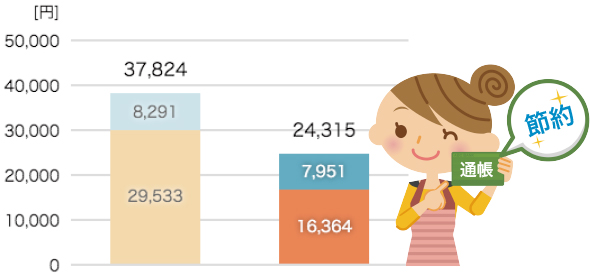
エコガラス商品の
ご紹介
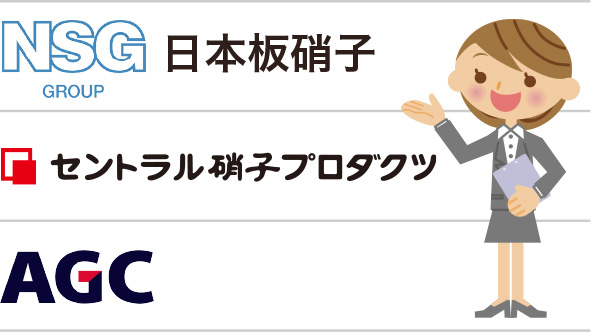
特別コラム
専門家スペシャルインタビュー(学術研究者)
エコガラス体験デモカー
「ガラスの森号」のご案内

冬の寒さ、夏の暑さ、エコガラスの効果はさわってみれば、すぐわかります。体感デモカーは夏と冬、どちらも体感いただける体感器を搭載しています。
その他の支援制度、
税制情報のご紹介
エコガラスサイトからのお知らせ
2024.02.19先進的窓リノベ2024事業についてのページを公開しました。
2024.02.19子育てエコホーム支援事業についてのページを公開しました。
2024.01.26エコガラス省エネシミュレーション(住宅版)を更新しました。
2023.04.20窓の性能表示についてのページを公開しました。
2023.04.20建材トップランナー制度についてのページを公開しました。