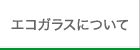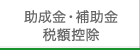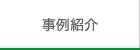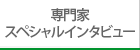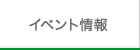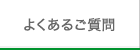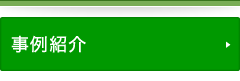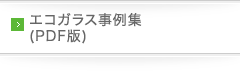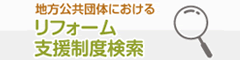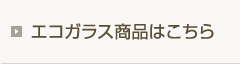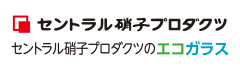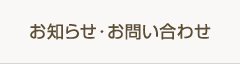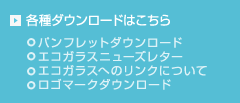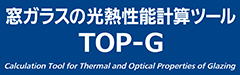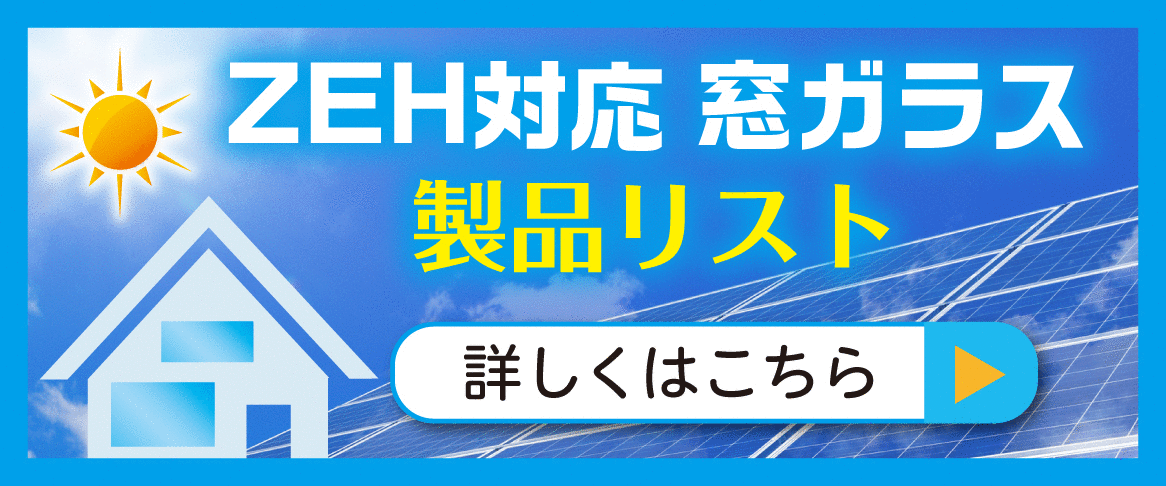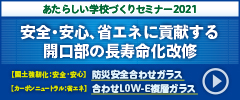長野県伊那市は南と中央ふたつの日本アルプスに抱かれ、天竜川・三峰川の一級河川を擁する自然豊かな土地柄。
祖父母の代から70年以上この地に暮らしてきたというS家が新しく建てた住まいは、まちの中心部にありながらも南アルプスの秀峰・仙丈ヶ岳をのぞむことができます。
「亡くなった父も大好きな山でした」と語るSさんにお話をうかがいました。
敷地は国道に沿い、河岸段丘の傾斜を背負っています。増築しながら数十年の歳月を重ねた旧宅は、前面道路からの振動と騒音、加えて古い家ならではの寒さと結露に耐えてきました。
新築を決めたSさんご夫妻の必須事項は“音と振動がない・寒くない”家。
それに加えて望んだのは「フェイクでない、本物の素材でつくること」です。木材や漆喰など天然の素材を使い、職人の腕や手づくりのテクスチャーが感じられる住まいを思い描きました。
本格的な木工を趣味とするSさんは、自分と奥さまの思いが一致したと笑顔で話します。
さらに“以前の家に使わない部屋がたくさんあった”経験から、家族の距離感を近く保ってコンパクトに暮らすことを旨としました。
当初は敷地も別に探してみたという、5年の月日をかけた家づくりです。住宅展示場をめぐり、多くの内覧会にも足を運んだご夫妻が最後に出会ったのは、東京で設計事務所を営む長谷川泉さんでした。
直線にして約150kmの“遠距離設計のわが家”はしかし、終始良好なコミュニケーションのもと、2018年10月に無事竣工を迎えたのです。